ロングライドはサイクリストにとって楽しみの一つだが、同時に疲労との戦いでもある。
100km、200kmと距離が伸びるにつれて体は悲鳴を上げ、楽しいはずのライドが苦行に変わってしまうことも少なくない。
しかし、疲労の原因を正しく理解し、正しい対策とることで、ロングライドを最後まで快適に楽しむことは可能だ。
この記事では、ロードバイク歴10年でロングライド・ブルベを走る筆者の数々の失敗と成功の経験に基づき、ロングライドの疲労を科学的な視点から分析し、具体的な対策を徹底的に解説する。
この記事でわかること
- ロングライドで疲労困憊になる科学的な原因
- ライド前・中・後に実践すべき具体的な疲労対策
- 疲労を軽減するための効果的なペース配分と補給戦略
- 意外と見落としがちな精神的な疲労への対処法
走行中の疲労対策にBCAAの摂取がおすすめ!
ロングライドの疲労、その正体とは?
ロングライドにおける疲労は、ひとつの原因で起こるものではない。
エネルギー不足、水分不足、筋肉のダメージ、そして神経系の疲れなど、様々な要因が複雑に絡み合って発生するのだ。
まずは疲労の原因を知ろう。
疲労の原因①エネルギー切れ(ハンガーノック)

ロングライドで最も警戒すべき疲労原因の一つが、エネルギー切れ、通称「ハンガーノック」である。
これは、体内に貯蔵されていた主要なエネルギー源である「グリコーゲン」が枯渇することで起こる。車で言えば、ガス欠の状態だ。
ハンガーノックに陥ると、以下のような症状が現れる。
ハンガーノックの主な症状
- 急にペダルが踏めなくなるほどの脱力感
- めまいやふらつき
- 強烈な空腹感
- 冷や汗
- 集中力の著しい低下
筆者も何度目かの300kmブルベに挑戦した際、このハンガーノックを経験した。
ライド中盤、100kmほどの地点で、日中であるにもかかわらず突然の睡魔と無気力な感覚に襲われ、ペダルを回す力が全く入らなくなったのだ。
道端に座り込み、持っていた最後の補給食を手で口に入れ、30分ほど動けなかった経験は今でも忘れられない。
このまま回復しないのならリタイア(DNF)しようと、電車の時間を確認していたが、なんとか再スタートできた。
原因は明白で、いつもなら定期的に補給していたが、そのときは計画的な補給を怠り、「お腹が空いたら食べればいい」という安易な考えで走っていたからである。
疲労の原因②脱水と電解質異常

エネルギー補給と同じくらい重要なのが、水分と電解質の補給だ。
長時間の運動では、発汗によって大量の水分と、それに含まれるナトリウムなどの電解質(ミネラル)が失われる。
体重のわずか2%の水分が失われるだけで、運動パフォーマンスは著しく低下すると言われている。
脱水が進むと、以下のようなサインが現れる。
脱水の主な症状
- 口や喉の渇き
- パフォーマンスの低下
- 尿の色が濃くなる、尿の量が減る
- 頭痛やめまい
- 筋肉の痙攣(足の攣り)
特に注意したいのが、足の攣りである。
これは単なる水分不足だけでなく、汗とともに失われたナトリウムやマグネシウムなどの電解質バランスが崩れることで引き起こされることが多い。
真夏に水だけをがぶ飲みしていると、体内の電解質濃度がさらに薄まり、かえって足攣りのリスクを高めることさえあるのだ。
疲労の原因③筋肉の損傷と乳酸

ペダルを回し続けるという行為は、当然ながら脚の筋肉に大きな負担をかける。
長時間の運動により、筋繊維には微細な損傷が蓄積していく。
これがライド後の筋肉痛や、ライド中の疲労感の直接的な原因となる。
かつては「乳酸=疲労物質」と考えられていた。
しかし近年の研究では、乳酸はエネルギー源として再利用される重要な物質であり、疲労の直接的な原因ではないという見方が主流である。
とはいえ、急激な高強度の運動によって血中の乳酸濃度が急上昇する状況は、体が無酸素運動に頼っているサインであり、持続不可能なペースであることの指標にはなる。
ロングライドでは、この乳酸が急激に増えないようなペースを維持することが重要だ。
疲労の原因④神経系の疲労(中枢性疲労)
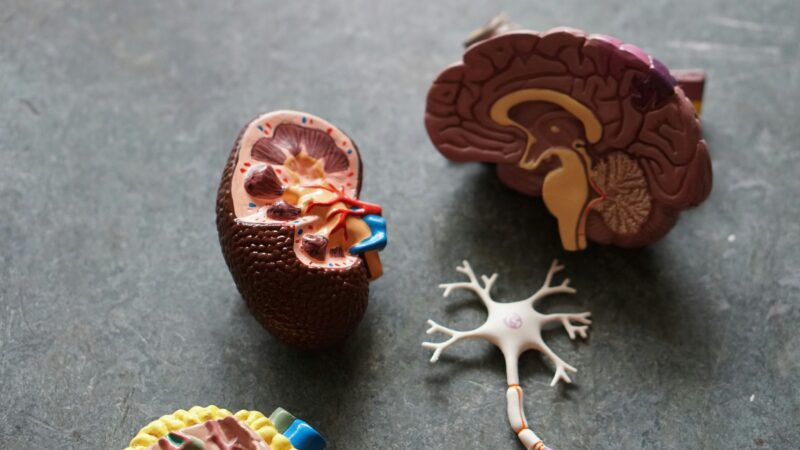
「疲れた」と感じるのは、筋肉だけではない。
実は、脳や脊髄といった中枢神経系も疲労するのだ。 これを「中枢性疲労」と呼ぶ。
長時間同じ姿勢を保ち、ペダリングを繰り返し、周囲の交通状況に注意を払い続けるという行為は、神経系に大きなストレスをかける。
自動車の運転であっても何時間もすれば疲れるのに、交通弱者の自転車は気にかけることばかりでもっと疲れる。
中枢性疲労が蓄積すると、集中力が散漫になったり、判断力が鈍ったりする。
「なんとなくやる気が出ない」「注意力が落ちてきた」と感じたら、それは神経が疲れているサインかもしれない。
この状態はパフォーマンスの低下だけでなく、落車などの事故に直結する危険な状態である。
疲労の原因⑤身体への物理的ダメージ

エネルギーや筋肉の問題とは別に、身体への直接的な物理ダメージも疲労を増大させる。
身体的なダメージ
- お尻の痛み・股ずれ: サドルとの長時間の接触と摩擦によって発生する。
- 手・腕の痺れ: ハンドルを握り続けることで、手のひらの神経(尺骨神経)が圧迫される「サイクリスト麻痺(ハンドルバー麻痺)」と呼ばれる症状。
- 首・肩・腰の痛み: 不適切なライディングポジションが原因で、特定の部位に負担が集中することで発生する。
苦痛に顔を歪める時間よりも、景色や仲間との会話を楽しむ時間の方がずっと長くなるだろう。
これらの「痛み」は、単に不快なだけでなく、痛みをかばうために不自然なフォームになり、さらに別の部位の疲労を誘発するという悪循環を生む。
精神的なストレスも大きく、ライドを楽しむ気持ちを削いでしまう厄介な敵だ。
身体の各部位の痛み対策について、それぞれの記事は下記。
【ライド前日】疲労を溜めないための準備戦略
ロングライドへの挑戦は、スタートラインに立つ前から始まっている。
前日の準備が、当日のパフォーマンスを大きく左右するのだ。
カーボローディングは必要か?

カーボローディングとは、レースなどの数日前から食事における炭水化物の割合を増やし、体内のグリコーゲン貯蔵量を最大化させる食事戦略である。
本格的なレースに臨むアスリートにとっては有効な手段だが、ホビーサイクリストの一般的なロングライドでは、それほど厳密に行う必要はない。
むしろ、慣れない食事法で胃腸に負担をかけるリスクの方が大きいだろう。
筆者が実践しているのは、ライド前日の夕食で、ご飯やうどん、パスタといった炭水化物を普段より少し多めに摂る、という程度の「プチ・カーボローディング」だ。
重要なのは、揚げ物などの脂質が多い食事や、消化に悪い食物繊維の多い食事を避け、胃腸に優しい食事を心がけることである。
ロングライド当日の朝食の考え方について、下記の記事でまとめている。
質の高い睡眠の確保

睡眠は、最高の回復薬である。
睡眠中に体はダメージを修復し、エネルギーを再充填する。
ライド前夜は、最低でも7時間以上の質の高い睡眠を確保することを目標にしたい。
興奮や不安で寝付けないこともあるかもしれないが、リラックスできる環境を整えることが重要だ。
- 寝る1〜2時間前には入浴を済ませる。
- 寝る前のスマートフォンやPCの操作は避ける。
- カフェインやアルコールの摂取は控える。
これらの基本的なことを守るだけで、睡眠の質は大きく向上する。
バイクの最終チェックと装備の準備

当日の朝、慌てて準備をすると、忘れ物をしたり、精神的な余裕がなくなったりする。
ライドで使う機材や装備は、すべて前日の夜までに準備を完了させておくのが鉄則だ。
- バイクのチェック: タイヤの空気圧は適正か。ブレーキはきちんと効くか。チェーンに注油はされているか。異音はしないか。
- 装備の準備: ヘルメット、グローブ、サイクルコンピュータ、ウェア一式、パンク修理キット、携帯工具、ライト類。
- 補給食の準備: 当日走る距離と時間から必要な補給食を計算し、すぐに取り出せるようにジャージのポケットやバッグに配置しておく。
機材トラブルは、余計な体力と精神力を著しく消耗させる。
筆者も、出先でパンクした際に予備チューブを忘れていたことに気づき、途方に暮れた苦い経験がある。
事前の準備は、リスク管理そのものなのだ。
ロングライドの装備・持ち物リストはこちらの記事で。
【ライド中】疲労を最小限に抑える技術
いよいよライド当日。
ここからは、走りながら疲労をコントロールしていく技術が求められる。
鉄則!「頑張りすぎない」ペース配分
ロングライドで最も多くのサイクリストが犯す過ちが、序盤のオーバーペースである。
走り出しは元気なため、つい気持ちの良いペースで飛ばしてしまいがちだが、これが後半の失速や疲労困憊に直結する。
「常に余力を残して走る」というのが、ロングライドの絶対的な鉄則だ。

ペースを管理するためには、心拍計やパワーメーターといった機材が非常に有効である。
もし機材がない場合でも、「笑顔で会話ができるくらいの強度」を意識すると良い。
息が弾んだり、会話が途切れたりするようなペースは、明らかに飛ばしすぎだ。
筆者も、ブルベではつい見栄を張ってペースを上げてしまい、100kmも走らないうちに脚が売り切れてしまった失敗が何度もある。
ロングライドは競争ではない。
自分の体と対話しながら、持続可能なペースを淡々と維持することが何よりも重要なのである。
ロングライドのための心拍数管理については下記。
「喉が渇く前」の水分・電解質補給

水分補給の基本は、「喉が渇いたと感じる前に、こまめに飲む」ことだ。
喉の渇きは、すでに体が水分不足に陥っているサインであり、そう感じる前に対処する必要がある。
目安として、15〜20分に一度、ボトルに口をつけ、一口か二口飲むことを習慣化しよう。
季節や強度によって必要な水分量は変わるため、以下の表を目安にしてほしい。
| 季節 | 1時間あたりの水分補給量の目安 | 補給のポイント |
| 夏場(高温多湿) | 750ml~1000ml | 積極的に電解質を補給する。ボトルの2本持ちは必須。 |
| 春・秋(快適) | 500ml~750ml | スポーツドリンクと水を併用し、糖分の摂りすぎに注意。 |
| 冬場(低温乾燥) | 500ml程度 | 汗をかいていないように感じても、呼吸で水分は失われる。温かい飲み物も有効。 |
そして、前述の通り、水だけではなく電解質を同時に補給することが極めて重要だ。
スポーツドリンクや、水に溶かすタイプの電解質パウダー、塩タブレットなどを積極的に活用しよう。
「お腹が空く前」のエネルギー補給

ハンガーノックを予防するためのエネルギー補給も、水分補給と同様に「お腹が空く前に、計画的に」行う必要がある。
体がエネルギー不足を感じてからでは、吸収・エネルギー変換が間に合わない。
一般的に、1時間あたり30g〜60gの糖質摂取が推奨されている。 これは、おにぎり約1個分、あるいはエナジージェル1〜2本分に相当する。
走り始めてから1時間後くらいから補給を開始し、その後も1時間ごとに定期的にエネルギーを摂取する計画を立てよう。
補給食には様々な種類があり、それぞれに特徴がある。
| 補給食の種類 | 特徴 | おすすめのタイミング |
| エナジージェル | 吸収が速く、即効性がある。携帯性に優れる。 | 疲労を感じ始めた時、峠の前など。 |
| エナジーバー | 腹持ちが良い。固形物なので満足感がある。 | ライド序盤~中盤の計画的な補給に。 |
| 羊羹・大福 | 脂質が少なく、糖質中心。日本人には馴染み深い味。 | ジェルやバーに飽きた時の変化球として。 |
| バナナ・おにぎり | 自然な食品。コンビニで手軽に入手可能。 | 休憩時の補給に最適。 |
複数の種類の補給食を用意し、味に飽きないように工夫することも、長丁場のライドでは意外と重要である。
補給に関する知識はこれらの記事で学んでほしい。
効率的なペダリングとフォーム
無駄な力を使わないことも、疲労を軽減する上で重要な技術だ。
重いギアを力任せに踏むようなペダリングは、筋肉への負担が大きく、早期の疲労に繋がる。
軽いギアを使い、ペダルの回転数(ケイデンス)を毎分80回転(80rpm)前後に保つことを意識しよう。
クルクルと回すようなペダリングの方が、心肺機能への負荷は大きいが、筋肉の消耗は抑えられる。

また、リラックスしたフォームを保つことも大切だ。
ハンドルを強く握りしめたり、肩に力が入ったりしていないだろうか。
上半身の力は抜き、体幹で体を支える意識を持つ。
そして、定期的にハンドルを握る位置(ブラケット、上ハン、下ハン)を変えたり、サドルから腰を浮かしてダンシングをしたりすることで、特定部位への圧迫や負担を分散させることができる。
休憩の取り方

休憩は、「疲れて動けなくなってから」取るものではない。
「これ以上走ると疲れが溜まるな」という一歩手前で、計画的に取ることが重要だ。
筆者は、50kmごと、あるいは2時間ごとを目安に、コンビニなどで5分〜10分の短い休憩を取るようにしている。
長すぎる休憩は、体が冷えてしまい、再スタートが億劫になるので避けた方が良い。
休憩中は、補給やトイレを済ませるとともに、軽いストレッチで固まった筋肉をほぐそう。
特に、屈伸運動やアキレス腱伸ばし、肩回しなどは効果的だ。
【ライド後】翌日に疲労を残さないリカバリー術
ロングライドは、自転車から降りた瞬間に終わりではない。
適切なリカバリーを行うことで、翌日以降の疲労度が全く変わってくる。
ライド直後のゴールデンタイムを逃すな

運動後30分〜1時間以内は、「ゴールデンタイム」と呼ばれている。
この時間帯は、体が栄養素を最も吸収しやすく、筋肉の修復が活発に行われる。
このタイミングを逃さず、タンパク質と糖質を素早く補給することが、効率的な回復の鍵となる。
具体的には、プロテインや糖質を含んだリカバリードリンクを摂取するのが最も手軽で効果的だ。
もし用意がない場合は、牛乳やオレンジジュース、おにぎりなどでも代用できる。
とにかく、ライドが終わったらなるべく早く、消耗した体に栄養を送り込むことを意識しよう。
クールダウンとストレッチ

ライドの最後に、いきなり自転車を降りて終わりにするのは良くない。
ゴール手前の5分〜10分は、軽いギアでゆっくりとペダルを回し、徐々に心拍数を落ち着かせる「クールダウン」を行おう。
これにより、血流が穏やかになり、疲労物質の排出が促される。
そして、自転車から降りた後には、時間をかけて入念なストレッチを行う。
特に以下の部位は、重点的に伸ばしておきたい。
- 大腿四頭筋(太ももの前)
- ハムストリングス(太ももの裏)
- ふくらはぎ
- お尻(臀部)
- 腰回り
- 肩甲骨周り
痛みを感じない、気持ち良い範囲で、各部位を30秒ほどかけてゆっくりと伸ばすのがポイントだ。
栄養バランスの取れた食事

ライド後の食事は、回復のための最も重要な要素の一つだ。
以下の栄養素をバランス良く摂取することを心がけよう。
- 炭水化物: 消費したグリコーゲンを再補充するため。ご飯、パン、麺類など。
- タンパク質: 損傷した筋繊維を修復するため。肉、魚、卵、大豆製品など。
- ビタミン・ミネラル: 体の調子を整え、回復を助けるため。野菜、果物、海藻類など。
難しく考える必要はない。
主食・主菜・副菜が揃った、日本の伝統的な「定食」スタイルの食事が理想的だ。
入浴と睡眠

ライド後の入浴は、体を清潔にするだけでなく、リカバリーにも効果的だ。
ただし、熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい、体の回復を妨げる可能性がある。
38℃〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かり、血行を促進させ、心身ともにリラックスするのが良い。
ただし、長湯はやめよう。筆者は20kmライド後に長湯しすぎて、脱水症状になってしまった経験がある。
そして、最後はやはり睡眠である。
ロングライドで疲弊した体は、質の高い睡眠を求めている。
ライド当日の夜も、できるだけ早く就寝し、十分な睡眠時間を確保しよう。
体が完全に回復するための、最後の仕上げである。
よくある質問(Q&A)

Q. 100kmの壁が越えられません。何が原因でしょうか?
A. いくつか原因は考えられるが、最も多いのは「ペース配分の失敗」と「補給不足」である。
序盤のハイペースで早々に脚を使ってしまい、さらにエネルギー切れや水分不足が重なって、後半に失速するというパターンが非常に多い。
まずは、スピードや平均時速を意識するのをやめてみよう。
その代わりに、「心拍数を一定に保つこと」と「30分〜1時間に1回の補給を徹底すること」を試してみてほしい。
ゆっくりでも走り続ければ、必ず100kmは達成できる。
Q. 足が攣ってしまいます。どうすれば予防できますか?
A. 足の攣りは、筋肉の疲労、水分不足、そして特にミネラル(電解質)不足が大きな原因だ。
水分補給を水やお茶だけで済ませていないだろうか。
汗で失われるナトリウムやカリウム、マグネシウムを補給するために、スポーツドリンクや塩タブレット、電解質パウダーの活用が非常に効果的である。
また、ライド前の食事でミネラルを豊富に含む食品(バナナ、海藻類、ナッツ類など)を意識して摂っておくのも良い予防策となる。
Q. お尻の痛みがひどくてロングライドに集中できません。
A. お尻の痛みは、多くのサイクリストが直面する根深い問題だ。
主な原因として、サドルの形状が自身の骨格に合っていない、バイクのポジションが適切でない、使用しているレーサーパンツ(ビブショーツ)のパッドが合っていない、などが考えられる。
対策としては、例えばライド中は30分に1回程度、意識的にお尻をサドルから浮かせる(ダンシングする)ことで、圧迫される時間を減らし、血流を促すのも有効な対策だ。
お尻の痛み対策については、下記の記事で詳しく解説しているので参考に。
まとめ:疲労を制する者がロングライドを制す

ロングライドの疲労は、単なる根性や気合だけで乗り越えられるものではない。
それは、エネルギー代謝、水分バランス、筋生理学、そしてメンタルが関わる、極めて科学的な現象なのだ。
疲労の原因を多角的な視点から正しく理解し、それに対する適切な対策を講じることが何よりも重要である。
ライド前には入念な準備を。 ライド中には計画的なペース配分と補給を。
そしてライド後には、体を労わるリカバリーを。
この記事で紹介した対策は、決して特別なものではない。
しかし、これらを一つでも多く、丁寧に実践することで、あなたのロングライド体験は劇的に変わるはずだ。
走行中の疲労対策にBCAAの摂取がおすすめ!










